
子どもが生まれた瞬間から、家計に「もしも」の備えが必要になります。
でも、保険って種類が多すぎて、何が本当に必要なのか分からない…そんな悩みを抱える子育て世帯は少なくありません。
この記事では、2児の父でありファイナンシャルプランナー(FP)でもある筆者が、実体験をもとに「入るべき保険」と「入らなかった保険」をわかりやすく解説します。
筆者自身は「公的保障で基本的なリスクに備え、貯蓄を優先して“万が一”に耐えられる体力をつける。そのうえで、心配な部分だけを保険で補う」という考え方をベースにしています。
目次
我が家で加入している保険一覧
家族構成
・夫(30代)
・妻(30代)
・子ども(3歳)
・子ども(0歳)
収入保障保険(夫)
補償内容・特徴:夫死亡時に月額15万が53歳まで家族に(最低期間2年)
目的・コメント:子育て期間中に夫が死亡した際、家族の生活費として活用するため。遺族年金をざっくり考慮し、生活費の不足分を確保する。
年間保険料:27,000円程
がん保険(夫婦)
補償内容・特徴:がん治療月10万〜15万、診断金、通院など
目的・コメント:貯蓄との兼ね合いで無くてもいいかもと思案している。家族に癌の人がいることと治療が長期になりやすいこともあり備えている
年間保険料:39,000円程(夫婦)
火災保険(賃貸)・個人賠償責任保険
補償内容・特徴:家財100万、修理300万、借家人賠償2000万、個人賠償責任特約、被害事故法律相談費30万
年間保険料:4,000円
目的・コメント:賃貸のため借家人賠償のため。家財もそこまで高額なものはない為最低限にしている。個人賠償責任保険は子供の事故や自転車事故による賠償に備えられる。
年間保険料:4,000円
なぜ私がこの保険に入ったのか?

必須保険(火災保険、個人賠償責任保険)
我が家で必須なのは火災保険と個人賠償責任保険です。賃貸に住んでいる為、物件契約時に必要になります。
ただ不動産会社ですすめる保険は2年間で2万円程するものが多く、私には過剰であった為契約時に自分で火災保険を契約すると伝え、証券のコピーを送っています。(不動産会社指定である必要はないはずだが対応してくれるかは不動産会社による為要相談)
個人賠償責任保険は自転車に乗る場合は加入が義務化されている地域が多い。一億円以上の保障があれば良く、使う機会がほとんどないため保険料は月数百円程度。火災保険や自動車保険、傷害保険の特約でつくことも多く、その場合は別途加入する必要はない。
重要度高保険(収入保障保険)
必須ではないが夫死亡時は家計へのリスクがかなり大きい為、収入保障保険等はほぼ必須と言える。公的保障としては遺族年金がある為必要な生活費から差し引きで不足する分をざっくり計算して設計した。我が家の場合は片親になると実家に帰省することを想定している為収入保障保険と遺族年金があればある程度生活できると考えている。
他にも終身保険や定期保険で備える方法もあるが収入保障保険にする事で、各年齢毎の必要保障の調整ができるためコスパが良いと考えた。
重要度中
最後はがん保険で、子育て初期の貯蓄が少ない頃に癌になった場合、親に頼ることになってしまう為加入した。実際には保険診療の範囲であれば高額療養費がある為、ある程度の貯蓄ができてきた今解約も検討しなくは無い。ただ親戚に癌の人がいることと2〜30代は女性癌のリスクもやや高い点を考慮して続けている。
加入しなかった主な保険と理由
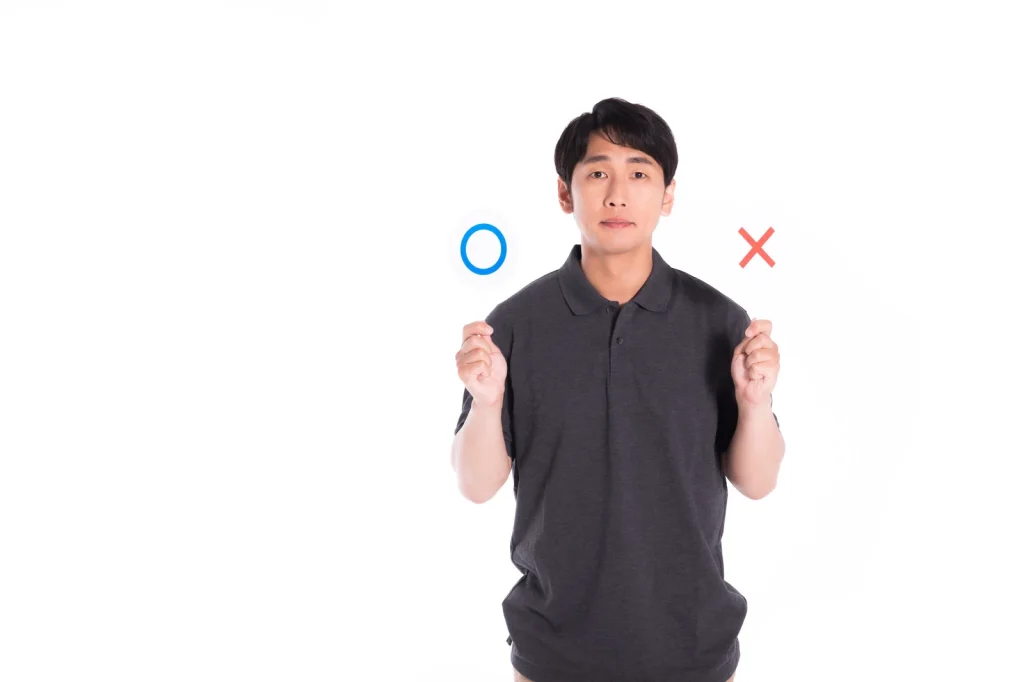
医療保険
加入しなかった理由
保険診療の部分には高額療養費制度があること、貯蓄で対応可能と判断したため。
補足
貯蓄が少ない方、あるいは自営業や個人事業主など収入減に繋がりやすい属性の方であれば検討しても良い。入院時には保険診療外の費用(差額ベッド代や食費、パジャマ代等…)もかかる。
🏥 高額療養費制度:69歳以下の自己負担限度額(月額)
| 所得区分(目安年収) | 標準報酬月額の目安 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| 区分ア:年収約1,160万円超 | 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 区分イ:年収約770万~1,160万円 | 53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 区分ウ:年収約370万~770万円 | 28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 区分エ:年収~370万円 | ~26万円 | 57,600円 |
| 区分オ:住民税非課税世帯 | ― | 35,400円 |
※最新の情報は厚生労働省や加入の健康保険組合などのホームページでご確認ください。
学資保険
加入しなかった理由
利率が低く、途中解約リスクがあるため。
補足
代わりに新NISAで教育資金を積み立てている。死亡時の保障はないがその分運用の自由度が高く、資産形成にもつながる。
終身保険・貯蓄型保険
加入しなかった理由
保障と貯蓄の目的が混ざっていて非効率と判断。
補足
保険料が高く、途中で見直しがしづらい。貯蓄は別で管理した方が家計が見えやすい。必要な死亡は掛け捨て最低限にしその分投資に回すほうが良いと考える。
自動車保険(任意保険)
加入しなかった理由
マイカーを持たず、移動は電車・バス・電動自転車が中心のため。レンタカーの際も基本保障のみ。久々の遠出で心配とかでなければ追加保障は入らない。
補足
基本保障でも対人対物などついており最大自己負担が15万円程のため不要と考えた。マイカーでも対人対物だけ無制限にして車両保障などは入らず自ら貯蓄でリスクを取る。
就業不能保険
加入しなかった理由
健康保険の傷病手当金が使えるためある程度は備えられること。またそんな状況になりそうなうつ病などは対象にならないことも多く使い勝手が悪い。
補足
自営業や個人事業主など国民健康保険の加入者は対象外のため検討の余地がある。
まとめ

保険は「入っているから安心」ではなく、「必要なリスクにだけ備える」ことが重要です。
我が家では、公的保障と貯蓄をベースに、必要最低限の保険だけを選び、過剰な不安や保険料の負担を手放すことで資産形成力を強められるよう意識しています。
保険も投資も、リスクとリターンはセットです。
「どこまで自分で備えられるか」を考えることで、
「どこまで保険料を節約できるか」も見えてきます。
まずは、自分がどんなリスクに備えたいのか、そしてそれをどうカバーするかを整理してみましょう。
この記事が、あなたの保険選びや家計の見直しのヒントになれば嬉しいです。
気になる保険や見直したい保障があれば、まずは「何が心配か?」から整理してみてくださいね。