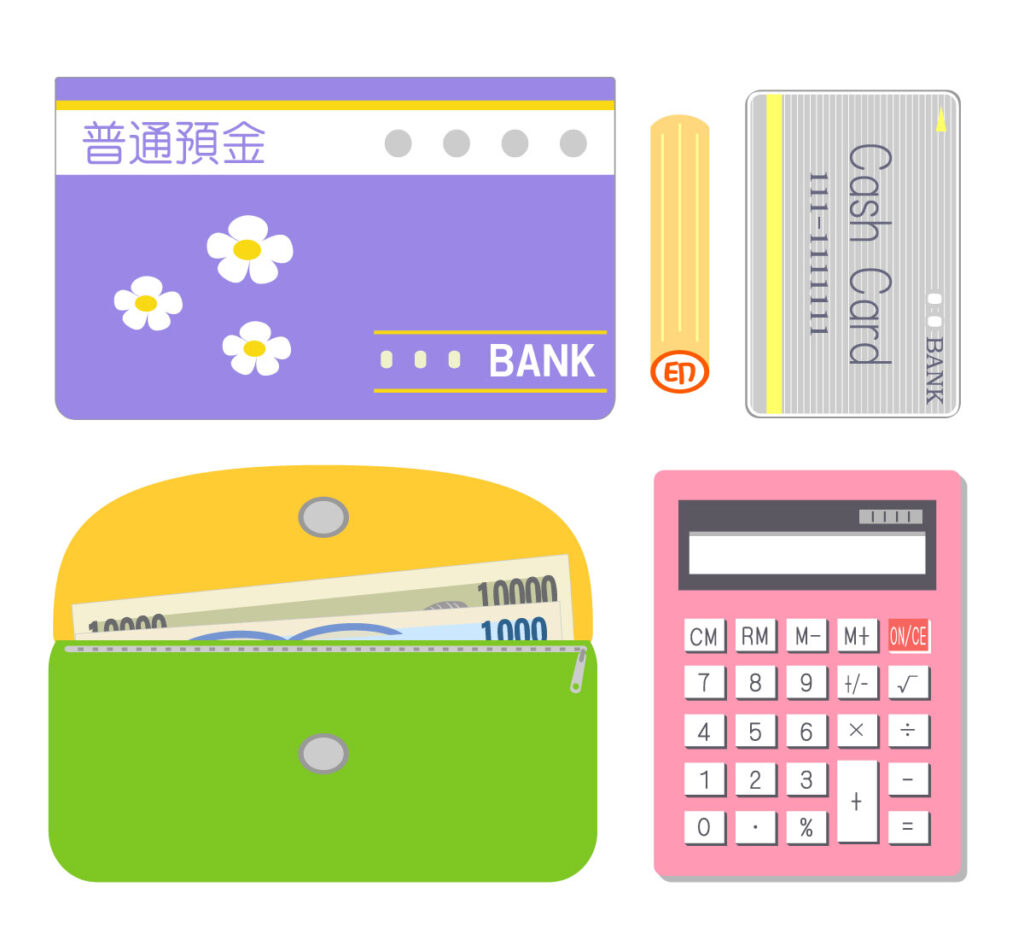新NISAに興味はあるけれどいまいち分からず不安だったり、何からはじめれば良いのか分からないと困っていませんか。
実はNISA制度ははじめてしまえばそこまで難しくありません。なぜなら一度設定してしまえば自動で積み立てていくことができ、都度売り買いしたりパソコンに張り付いたりする必要がない投資方法だからです。
私は子供を育てるのに将来の教育資金や自分の老後の資金などに不安がありましたが、NISA制度を利用することで資産形成に自信がつき、計画的に資産形成できるようになりました。
この記事では新NISAの基本的な仕組みを解説し、おすすめの証券会社や投資先をお伝えします。
これを読むことで投資初心者の方が安心して新NISAを始められるようお手伝いします。
この記事を読んだ後で証券口座を開設し、積立設定をすれば、後は毎月コツコツと自動で積み立てていけるようになります。
新NISAとは?
NISAとは少額投資非課税制度のことで、投資による資産形成を支援するため、株式や投資信託などの一定の投資商品に対する税金を非課税にするものです。
通常は利益に対して20%の源泉徴収税がかかりますが一定の範囲で非課税になります。
これまではつみたてNISAと一般NISAの二本立てでしたが2023年末で終了し、その二つを統合するような形で新しく開始したのが新NISAです。
新NISAの概要
・新NISAには投資枠が二つあり、『つみたて投資枠』と『成長投資枠』という。それぞれで投資先や利用可能額、運用方法などに違いがあるが、基本はつみたて投資枠を用いて毎月一定額ずつ投資するところから始めるのがおすすめ!
・非課税保有期間が無期限化したため、老後まで運用する事も可能となった。
・年度毎限度額はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で合計360万円までです。
・通算保有限度額は合計は1800万円までで、そのうち成長投資枠は1200万円までです。つみたて投資枠だけで1800万円使うことはでき、成長投資との併用も可能だが成長投資枠は1200万円が限度である。
・保有限度額の枠は再利用は可能で売却した分の購入費用分が復活する。ただしその場合でも年度毎の利用限度額は次年度まで復活しません。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 投資対象 | 投資信託が主 | 個別株、投資信託、ETF、REITなど |
| 年度毎限度額 | 120万円 | 240万円 |
| 保有限度額 | 1800万円(内、成長投資枠は1200万まで) | |
| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
・投資先の銘柄などは金融庁が絞り込んだもののため初心者にも比較的選びやすいですが、どれでもいいわけではありません。
成長投資枠とは?

成長投資枠はつみたて投資枠に対して投資対象になる商品が多く、個別株なども含まれます。また、つみたて投資枠が定期的な購入なのに対し、いつでも購入可能な点からも短期~中期的な運用がしやすいです。
先に述べた通りつみたて投資枠を用いて始めることをお勧めしましたが、それではどんな時に成長投資枠を使うのか例を解説します。
・つみたて投資枠を使い切ってさらに投資したい場合で、例えばつみたて投資枠は年間120万までのため、月10万以上行う場合は成長投資枠での投資を行うことになる。
・個別株などを購入したい場合で、例えば日本株や米国株、ほかにもETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)などがある。
・短期的~中期的に売買をしたい場合で、例えばつみたて投資枠では毎月何日にいくら積み立てるとあらかじめ設定するため、買い付け確定するまではっきりした基準価格(株などの単価)などはわからないが、成長投資枠では市場が開いている時であればリアルタイムで売買が可能であったりする。
初心者の方はまずは、つみたて投資枠で初め、少しずつ慣れたら成長投資枠を利用するか検討すれば良いでしょう。
メリット、デメリットは?

メリットとしては、長期間の分散投資によって運用益が見込めることです。世界経済は少しずつ成長していくと見られていて、人気の世界株式の指数にそった投資信託を選ぶことで、世界が成長すれば価値が上がるという構造で、長期保有した際には3〜7%程の運用益が過去の実績からも見込まれています。
またその利益が非課税になること、最初に設定して仕舞えば後は基本的に自動で支払いをしていくだけで常に株の売買をしたりチェックするような手間は基本要りません。
仮に月3万を20年間、5%で運用できたとして元本720万に対して、513万円程の利息がつきます。税金が20%取られた場合は100万円程税金に溶けるわけですからここが非課税になる点が大きいです。
デメリットとしては、あくまで投資であり元本が保障されるわけではないということ。特に短期間での運用であれば元本割れになる可能性は十分にあります。
一方で15〜20年以上の長い期間にわたって分散投資していれば、ドルコスト平均法の観点や世界経済が緩やかに発展していることなどから、比較的リスクは下がるとされています。
暴落時でも一定額でコツコツ続けることも大事なので不安になって売却しないようにある程度知識をつけておきましょう。
新NISAの始め方とおすすめ銘柄

これまでつみたてNISAをしていた方は増額が可能であれば検討しても良いでしょう。
つみたてNISAをしておらず、今回の制度から始めてみようと思った方は、証券口座をお持ちでない方が多いでしょうからまずは証券口座を開設しましょう。
おすすめは楽天証券かSBI証券で、この二つであればどちらでも選べる投資先も多く、ポイントが貯まったりもしますのでおすすめです。
楽天のサービスをよく使う方は楽天証券、三井住友銀行系やvポイントの経済圏の方はSBI証券がいいかと思います。
一度選ぶと基本的にそこの証券会社で続けるのでこだわりたいって方はより詳しく調べてみてください。
口座開設には本人確認など含めて数週間かかると思います。始めようと思った方はまず口座開設しておいてください。
おすすめの投資信託

最後におすすめの投資信託ですが、全世界株式型の投資信託をお勧めします。なぜなら世界の株式に分散して投資信託を作っているためバランスが取れており、分散されているためリスクが下がります。
あとは運用コストが極力安い投資信託を選ぶことで、長期運用した際により利益が見込めるようになります。
決められないって方は『eMAXIS Slim全世界株式』にしておくと、比較的コストが低く分散投資の観点からも人気が高いので良いでしょう。
※利益を約束するものではありません。投資は自己判断でお願いします。
まとめ
2024年1月から新NISAが始まりました。制度変更はあるものの最初の設定さえしてしまえば後はほとんど手間にはなりません。投資は早く始めることで複利の力がより働き結果に差が生まれます。
まずは証券口座の開設、そしてつみたて設定までを行う。この記事をきっかけに理解が深まり新NISAを利用する方の助けになれば幸いです。